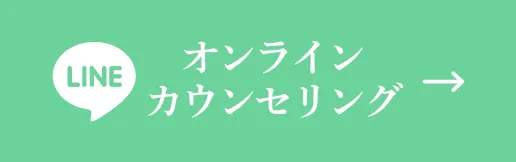患者様からの歯科治療に関する
お問い合わせから、
よく頂戴するご質問をまとめました。
その他にもご不明点がございましたら
お気軽にご連絡下さいませ。
治療方針について
- とりあえず今の現状の相談だけ
したいのですが、
それでもいいですか? -
「他の医院で治療を受けていたけど不安になってきたのですけど・・」
「もう何年も歯医者に行ってなくて・・・」
「他の歯医者で歯を抜かないといけないと言われたのだけど、本当に抜かなくてはいけないの?」
「加藤総合歯科・矯正歯科では金属の詰め物を白くしてくれると聞いたのだけど、私の歯もできますか?」
など、様々な理由で皆様来院されます。加藤総合歯科・矯正歯科ではまず最初に現状をチェックさせて頂き、患者様とじっくりお話をし、希望内容、希望する治療回数、希望する治療期間など、できるだけご要望にそった治療計画をたてていきます。
まず、患者様が何を望んでおられるかが一番大事なことだと思っていますので、遠慮なさらずに希望をおしゃって下さい。
また、大阪の羽曳野市にある加藤総合歯科・矯正歯科では様々な医療機関とも連携をとっています。
医科や大学病院とも必要があれば連携をとり、どうすれば患者様にとって一番よいのか、何度もお話をさせてもらいながら治療をすすめていきます。まずは、お気軽にご相談下さい。
- 遠方から来ているので
まとめて治療して欲しい
のですができますか? -
大阪の羽曳野市にある加藤総合歯科・矯正歯科は遠方から治療にこられている方も多く、仕事のご都合や、学校行事、旅行などである一定期間来院できない事情ができる場合もあると思います。
また、とりあえず応急処置だけ行って欲しいという方もおられます。私たちの方針を理解していただき、継続的にしっかりとした治療を受けていただくことが前提であればお困りのところを診させたいただくことは可能です。
しかしながらお仕事のためにご予約のキャンセルが多くなられたり、次のご予約がお取りしにくくなりますと、責任のある治療をご提供さし上げることができなくなります。加藤総合歯科・矯正歯科では歯をしっかりと治し、健康度を向上させ、その上で仕事に全力で取り組んでいただくことを応援させていただきます。
- 治療回数はどのぐらい
かかるのですか? -
これは虫歯の状態や歯周病、根の病巣があるかないかなどによって変わってきます。
通常は基本治療(根管治療や歯周病治療など)を重視して、しっかりとした土台作りから始めますので、治療後長持ちするためにも「急がば回れ」をお薦めしております。
しかしながら遠方の方や通院が困難な方のために、できるだけ通院回数を少なくすることも承っております。可能な限りご都合に合わせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせくださいませ。
- 加藤総合歯科・矯正歯科の
予防治療とは
どんなものですか? -
虫歯の予防
1)低年齢児における母親からの感染予防
2)適切な食事の内容と回数
3)積極的なフッ素の利用
4)補助的な化学的予防(キシリトールなど)
5)適切なホームケアと定期的なプロフェッショナルケア歯周病予防
1)夫婦間、家族間における歯周病菌の感染予防
2)化学的な歯周病のリスク判定
3)喫煙のコントロールと全身的疾患(糖尿病など)の予防
4)毎日の適切なプラークコントロール
5)歯周病菌のバイオフィルムの機械的除去
6)歯周病菌の化学的抑制(抗菌剤、抗生物質、クロルヘキシジンなど)
7)定期的なメインテナンス以上のように加藤総合歯科・矯正歯科では予防治療にも力を入れています。
加藤総合歯科・矯正歯科の歯科衛生士にご相談下さい。
- 保険内で同じ治療をしたはず
なのに治療費が違うのは
なぜですか? -
保険診療は、国が定めた治療体系(保険点数)ですべて行われますので、
全国どこの保険診療機関で治療を行っても、同じ治療であれば同じ治療費となります。ただ、この治療費は細分化された治療行為一つ一つに決められている保険点数の合計で算出されています。
そのため、虫歯治療で金属やプラスチックを詰める処置を受けても、詰める範囲や、
前歯か奥歯かでも保険点数が異なるため、治療費も同じではありません。
歯石取りなどでも同様になります。さらに、歯磨き指導料や歯周病の管理料などが保険制度のルールに従って発生するため、
同じ治療のようでも細かい処置内容の違いや時期の違いにより、多少治療費が異なります。患者様からみて細かな治療違いを感じていただくことは難しいためできるだけ細かな説明と会計の時に
明細書をお渡ししていますが。
もし疑問がありましたら遠慮なくお尋ね下さい。
診療内容について
- 歯をたくさん削らないと、
詰めたり、かぶせたり
できませんか? -
大阪の羽曳野市にある加藤総合歯科・矯正歯科ではM.I.という考え方を一番大切にしています。
患者様ご自身が持つ自然な歯を、できるだけ削ったり、抜かず、神経も抜かない方針をまず何よりも最優先にさせて頂いています。虫歯が大きい場合は歯を守るためにセラミックスはよく使います。
逆に小さな虫歯の場合(世界的な保存治療のプロトコルに合わせ虫歯の幅が2mm以下の場合にレジン治療に優位性がありますので)レジン充填を行います。あまり歯を削らなくて済むレジンによる修復や、グラスファイバーやレジンコアを用いたブリッジなどのご提案もしています。健全な歯を削ってのブリッジは極力避け、歯やからだに優しい義歯をおすすめすることも多々あります。歯周病治療も同時進行に行い歯肉や歯周組織から健康な状態に持ち上げ、患者様が本当にご自分の歯を大切にしていただけるよう治療方法をご提案いたしております。
- できるだけ痛み無く
治療してほしいのですが? -
大阪の羽曳野市にある加藤総合歯科・矯正歯科では麻酔自体は最初に表面麻酔を必ず行いますのであまり痛くなく行われます。麻酔の時の痛みというのは、実は術者の技術力によるところがほとんどです。ぜひ歯科の注射は怖い、痛いとばかりお思いの方は、従来までのその認識がくつがえるご体験をなされることをお薦め致します。
ただし、麻酔を行うことのできない治療や、あえて歯を削りすぎないために麻酔を行わない治療、内科的に麻酔のお薬が使いにくい方もおられますので、その時は内科主治医先生と連絡をとりながら麻酔を行うことがあります。根の消毒の治療などにおいては消毒剤が患部に入っていくときに、少し痛みを感じられることもあります。全てが痛みのまったく無い治療でまかなえるわけではありませんが、私達加藤総合歯科・矯正歯科では、できるだけ患者様が痛みや苦痛を感じることなくお過ごしいただけますよう、いつも細心の注意を払って治療を行なっています。
- 保険でも前歯に白い歯を
かぶせることができると
聞いたのですが? -
はい、可能です。
保険の前歯は硬質レジン前装冠と呼ばれていて、金属にプラスチックを貼り付けたものです。
欠点はオールセラミックスに比べて水を吸いやすく変色が起きます。
また、裏側は金属ですので腐食が起こりやすくアレルギーなどの心配もあります。前から4番目、5番目の歯は保険でCAD/CAM冠というものです。全周がレジンという
白い素材で治療可能で、金属を使わないので見た目がきれいに治療することができます。
欠点はオールセラミックスに比べ強度が弱いために、たまに硬いものを噛むと割れることがあります。
- 虫歯をつめた隙間から
また虫歯ができてといった
再治療の繰り返しで、
ついに歯を抜くことに
なってしまいました。
歯が弱くて虫歯になりやすいと
言われたのですが
仕方ないのでしょうか? -
確かに虫歯のなりやすさには個人差があります。
唾液中の虫歯菌の量、唾液そのものの性質(緩衝能)、唾液の分泌量、歯の質などからです。しかし、最も大事なことは虫歯治療の質の方だと考えています。唾液中には虫歯菌が数多く存在し、治療中や仮づめ、仮歯の間に唾液による細菌感染を徹底的に防ぐ事がとても大切です。人口エナメル質のバリアによる修復前処置、さらに詰め物やかぶせものが歯との段差や隙間が無くぴったりと合ってることなどすべてにおいて精度の高い治療レベルが虫歯再発防止のためには欠かせません。術後の検診やご自宅でのケアなど、管理をしっかりしていただくことも大切です。
また、ドライマウスになると虫歯はもちろん歯周病も加速度的に悪くなります。加藤総合歯科・矯正歯科では歯や歯周組織だけでなく、口腔全体から患者様の健康をサポートいたします。
- 詰め物による環境ホルモンの影響はないですか?
-
いわゆる環境ホルモンとしてのビスフェノールAのことをお尋ねのことと思われます。
環境ホルモンは、人体において女性ホルモンと同様の働きをし、精子の減少、メス化など、体内の機能をかく乱させる作用があると考えられています。
NHKスペシャルや、民放、週刊誌等で歯科用材料から唾液中にビスフェノールAが溶け出すということが報道されたことを心配してのことと思います。歯科用材料の中の、コンポジットレジンやシーラントと呼ばれる白いつめものの中に、ビスフェノールAが存在しますが、単独ではなく、ビスGMAと呼ばれる成分の1つとして存在しており、容易に溶け出すことはありません。
米国歯科医師会は、シーラント材からごく微量のビスフェノールAが溶出されたとしても、血液中に検出されなかったとして、危険性もないとしています。
日本歯科医師会は「現在市販されているコンポジットレジンおよび歯科用シーラント材のほとんどには、ビスフェノールAの存在は確認されず、たとえビスフェノールAが認められたとしても、
血液中に移行しないということから、健康への障害は考えられない」とする、学会よりの報告を受け、安全性は確認されています。
- 冷たい水でしみる時と、
熱いお湯でしみるときの違いは
どのようなものでしょうか?
また治療はどんな方法が
ありますか? -
歯の神経(歯髄)の炎症の程度の違いにより、症状が異なってきます。
冷たい水でしみるときは、う蝕による場合や、歯髄に炎症があってもまだ初期の段階であるといえます。
しかし、冷たい水では感じず、熱いお湯で痛みを感じる ようになってきた場合、う蝕の原因となる細菌が歯の神経(歯髄)の方まで進み、歯髄の大部分が炎症をおこしているものといえます。冷たい水でしみている時期であれば、歯のしみ止めの処置で治まりますが、熱いもので痛みを感じるようになると、歯の神経(歯髄)の炎症が悪化していますので最終的に歯の神経を取る処置をしないといけなくなってしまいます。
初期症状の段階であれば歯の表面の薬を塗布したり、レジンを詰める処置で治りますのでお早めにご連絡下さい。
- 以前ズキズキ痛んだ歯が薬を
飲んで7日くらいで痛みは
なくなりました。
放っておいて大丈夫ですか? -
虫歯は放置しておくと、ますます悪くなるので早めの治療が大事です。
歯には神経があり、大きな虫歯ができるとその神経を刺激してズキズキ痛みます。
しかし、そのままにすると一度歯の痛みが消えるときがあります。
これは歯の神経が腐って死んでしまったためで、決して治ったわけではないのです。
(皆さんは歯が治ったと思い勘違いされて後日大変なことになるのですが・・・)早めに治療をすれば痛んだ歯を抜かずに治療できる可能性が高いですが、何ヶ月も放置してしまいますと、今度は自覚症状なしに神経が化膿してきます。
この時点で、もう歯を抜かないといけなくなります。さらに、たまたま痛みがないなどで放置し続けると顎の骨までとけていきます。
歯の痛みが一旦おさまったと思っても油断せずにできるだけ早く歯科医師に相談して下さい。
- 歯の神経を取る治療を
しましたが、歯が熱いものに
しみます。 -
歯の神経の治療は直接見ながら治療ができないため手の感覚を研ぎ澄まして行っていきます。
神経の治療には特に歯科医師の技術と経験が必要になってきます。今回のお話ですと、神経をとった歯が痛いとしたら、残髄炎という事が疑われます。
歯の神経は、途中で分岐している事があり、この分岐した神経はまず取り切れません。
そこで薬品で落ち着かせるのですが、充分な時間と回数をかけてもこの残った神経に炎症が出てしまう場合があります。ご自分がその歯だと思われるなら、歯科医にご相談ください。
それでも分かっていただけない場合は、転院も一つの方法だと思います。
残髄炎自体は不慮のものであり「医療ミス」ではありませんが、患者さんと歯科医の間に信頼関係がなければ、治療に障害が出ることがあります。
料金について
- 医療費控除の対象に
なりますか? -
はい、適用可能です。
領収書の再発行はできないので、当院でお支払いされた領収書を大切に保管してください。
- 保険は適用されますか?
-
治療によっててきようされるものとされないものがあります。
一般的な虫歯治療や歯周病治療などは保険適用となりますが、インプラントや歯のつめもの・かぶせものをセラミック製にかえる審美治療は自費となります。
- クレジットカードは
使えますか? -
ほとんどのクリニックが保険診療ではクレジットカードが使えない中、当院では感染症予防や利便性を考え、保険診療 自費診療 共に現金はもちろん、各種キャッシュレスがご利用いただけます。
- キャッシュレスは何が
できますか? -
PayPay、ID、交通系iCカードが使用できます。
- デンタルローンについて
-
当院では「アプラス」のデンタルローンをご案内させていただいております。
歯科治療費をアプラス社が患者様に代わって当院に対して立替払いするローン契約です。患者様のご計画に合わせた分割による支払プランをお選びすることができます。
また、24回払いまで金利は当院が負担しております。※その他、エポス、スルガ銀行のデンタルローンもご利用いただけます。
その他

歯ブラシについて
- むし歯予防や歯周病予防に
効果的な歯みがき方法は
ありますか? -
まず、力を抜いて歯ブラシできるように肩の力を抜いてリラックスしましょう。
首を軽く回して頂くのもいいと思います。次に、歯ブラシの持ち方は鉛筆持ち(ペン持ち)にして歯ブラシの一番お尻の部分を軽く持ちましょう。
グッと持たずに軽く持つのがポイントです。
歯みがきは歯を1~2本ずつわけて、ていねいに行います。
歯ブラシの毛先は歯と歯ぐきの境目に斜め45°度の角度であてます。
奥歯、前歯、歯の外側、内側と順序よく、歯ブラシを上手に動かしましょう。
ゴシゴシこすらずに、歯ブラシを細かく振動させるように動かします。
前歯の裏は歯ブラシのかかとを使って行って下さい。歯周病は夜に進行すると言われています。夜の寝る前の歯ブラシは特に入念に行って下さい。
- 歯ブラシをすると歯肉から
血がでます。大丈夫ですか? -
おそらく軽い歯肉炎があるのだと思います。
歯肉炎を改善するためには、歯と歯ぐきの境目や、歯と歯の間をきちんと磨くことが大切です。
歯みがきの時に痛みがなければ「ふつうの硬さの歯ブラシ」で、歯ぐきが腫れて痛みがある時は「やわらかめの歯ブラシ」で、ていねいな歯みがきを続けましょう。奥歯のほっぺた側を磨く時は「イー」の口をさせて、歯ブラシを奥に入れ、横に細かく歯ブラシを動かします。
できれば口角(唇の端)から人差し指を入れ、ほっぺの内側を引っ張り、空間を作ると歯ブラシを動かしやすいでしょう(奥歯の内側は少しでも口を開けないと難しいですね)。
ただ、力を入れすぎないように気をつけましょう。歯周病は夜に進行すると言われています。
夜の寝る前の歯ブラシは特に入念に行って下さい。
- 電動歯ブラシはどのような人が
使うとよいのですか? -
年齢が若い時には言われなかったのに、最近「歯間ブラシ」や「デンタルフロス」を使うように勧められることはよくあると思います。
これは、元々歯ブラシだけでは、歯と歯のすき間にみがき残しが生じる上に、中高年を過ぎると、歯ぐきがやせて、歯の根の部分(歯根)が見えてきて、歯が長くなったように見えるためです。
この歯根のすき間には、歯垢や歯石がたまりやすいので注意が必要で、
徹底的に歯ブラシを行う必要があります。そこで、「歯間ブラシ」や「デンタルフロス」で、歯と歯の間や歯根と歯根のすき間をていねいに磨けば、歯周組織がきれいになります。
歯間ブラシは歯のすき間に合わせて大きさを選んで下さい。
もし、ご自分の歯間ブラシのサイズが分からないときは歯科衛生士にご相談下さい。
- フッ素入りの歯みがき剤は、
どんな効果がありますか? -
家庭で使えるフッ素の代表として「フッ化物配合歯みがき剤」があります。
低濃度であるため、毎日使うことにより、良い歯の質を保つことやむし歯予防に効果があるといわれています。
特に、子供の永久歯がまだ弱く虫歯になりやすい時期や、中高年の歯の根の部分にむし歯が増える時期に効果的です。
しっかりとした科学的根拠、効果があるため是非、使用することをお勧めします。ただし、歯磨き粉をたくさんつけて強くゴシゴシ磨くと、歯や歯ぐきが傷つくことがありますので、少なめにつけて磨きましょう。
- 毛の硬さや材質はどのような
歯ブラシがよいのでしょうか? -
毛の硬さは、普通から少し硬めのほうが効率よくプラークを除去できます。
しかし、歯肉に炎症があり、赤く腫れている場合は、初め比較的柔らかい歯ブラシを用い、病気が改善したら普通の硬さの歯ブラシに変えるとよいでしょう。現在、毛の材質は、需要の関係から天然毛(豚や狸の毛)も生産されていますが、規格製品の作りやすさから、そのほとんどはナイロンが使用されています。
ナイロン毛は抗菌処理、先端の丸形加工ができたり、水はけがよく衛生的であり、清掃効果も天然毛よりすぐれています。
- 歯ブラシを買い替える目安を
教えてください -
期間としては約1カ月といわれていますが、歯ブラシを裏から見て、毛先が飛び出して見えるときが替える時期だと覚えてください。
なぜなら、毛が曲がっていますと、プラークを取り残しやすい歯と歯の間や歯と歯肉の境目などに、毛先がうまく当たらなくなり、清掃効果が悪くなるからです。
その上、歯肉を傷つけることもあります。早めの交換をお勧めします。極端に交換時期が短い方は歯ブラシの力が強すぎますので、優しくブラッシングを行って下さい。
- 介助磨きの時、口を大きく
開けないので奥歯に磨き残しが
できます。 -
介助磨きの時に、どうしても口を大きく開けれないために磨き残しができることは、よくありますし、口腔ケアを考えた時に、可能な限り清潔にしたいところですね。
介助磨きのコツは、奥歯のほっぺた側を磨く時は「イー」の口をさせて、歯ブラシを奥に入れ、横に細かく歯ブラシを動かします。
できれば口角(唇の端)から人差し指を入れ、ほっぺの内側を引っ張り、空間を作ると歯ブラシを動かしやすいでしょう(奥歯の内側は少しでも口を開けないと難しいですね)。
注意点は、どうしても磨くことに集中しすぎると力んでしまいます。
力を入れすぎないように気をつけて下さい。

トリートメントケアについて
- 歯の掃除とトリートメントケア
はどう違う? -
「歯のお掃除は歯ブラシで届かないプラークを専用の機械と研磨ペーストで綺麗にすること」
例えば…
髪の毛のシャンプー…そのままだとパサパサになりますよね?
洗顔…そのままだと突っ張りますよね?
車の水洗い…水洗いだけだと汚れが付きやすいですよね?「トリートメントケアは、目に見えない細かな傷に、歯と同じ成分を埋め込んで滑らかにすること」
例えば…
シャンプー後のトリートメント
洗顔後の美容液
洗車後のワックス「トリートメントケアを受けると…」
・ステインが付きにくくなるので、お茶やワインを好きなだけ飲めますよ
・歯が強くなるので虫歯の心配がありません!続けると生涯自分の歯で食事ができます!
・プラークがつきにくくなるのでブラッシングが楽になります
・やればやるほど歯面にツヤがでるので、笑顔に自信が持てます
・何度でも好きなだけ受けられます
- どのくらいの間隔で行えば
いいのですか? -
理想的には1ヶ月に一度ずつ続けることでより健康で美しくなりますので、継続することをお勧めします。
ただ、お忙しくてなかなか時間がとれない方が多いので、大阪の羽曳野市にある加藤総合歯科・矯正歯科では歯と歯肉のメンテナンスと並行してトリートメントケアを集中的に行い、できるだけ短期間で終わるようにしています。
ただ個人差もありますので、詳しくは歯科医師、歯科衛生士にご相談下さい。
- 歯周病があるのですが
問題ないですか? -
歯周病の人は歯の根が露出している場合が多いため、トリートメントケアをぜひお勧めします。
歯の根の主成分である象牙質の70%がハイドロキシアパタイトで構成されていますから、ナノ粒子ハイドロキシアパタイトの働きにより、再結晶化も可能です。歯のブラッシングやクリーニング時に根に対して研磨粒子を過剰に使用すれば知覚過敏を引き起こす恐れがありますので、研磨剤を使用した後のトリートメントケアをお勧めします。
詳しくは歯科医師、歯科衛生士にご相談下さい。
- 内科等で病気を治療中です。
大丈夫ですか? -
内科等で病気を治療されている方こそトリートメントケアはお勧めします。
なぜなら、トリートメントケアは審美的な回復も可能ですが、歯質を強化し、う蝕になりにくい状態にすることができます。
つまり歯の状態が悪くなると処置も大きくなり、歯の治療が体に負担をかけてしまうことを予防することになるのです。歯面や根面を滑らかにすることによってプラークが付着しにくくなり、リスクコントロールにもつながります。
特に最近の研究では歯周病菌が心筋梗塞を引き起こすことも分かっており、心疾患でステントやバイパス手術をされている方のリスクを下げることができます。詳しくは歯科医師、歯科衛生士にご相談下さい。

妊娠期について
- 妊娠中に歯が弱くなる
というのは本当ですか? -
確かに、妊娠中はむし歯ができやすかったり、歯肉炎を起こしやすかったりします。
俗に、妊娠中だと歯のカルシウム分が胎児にとられるため、母親の歯が弱くなると言われていますが、歯は一度歯ぐきから生えた後、身体のカルシウム代謝と関係がなくなりますので、歯からカルシウム分が取られてしまうことはありません。では、いったい何が主な原因になるのでしょうか?
妊娠中は生活のリズムの変化やつわり等で食生活が変化し、歯磨きがおろそかになったり、口の中の衛生状態が悪化することがあります。
また、女性のホルモン分泌のバランスが変わり、妊娠性歯肉炎を起こしやすくなります。
したがって、妊娠中は規則正しい食生活をして、歯磨きを丁寧に行い、お口の中を清潔に保つことが必要です。また、最近歯周病により早産・低体重児出産のリスクが高まることがわかっています。
妊娠を予定している場合はぜひとも歯科健診を受けていただきたいて、歯と歯周組織のメンテナンスを是非受けてください。
- 妊娠中の虫歯の治療は
どうすればよいですか? -
身体の状態が安定していると言われる妊娠中期(4~7カ月)が歯科の治療を受けるのに最も適した時期と言えるでしょう。
妊娠初期は、さまざまな器官の基本的な部分を形成していく時期であり、エックス線や薬の使用に少々気を使います。
またつわりも生じてくるので、あまり治療には向いてない時期となります。妊娠後期では、初めのころは比較的安全ですが中盤以降は胎児も大きくなり、長時間の診療ができなかったりちょっとした刺激で早産につながってしまう事態も考えられます。
基本的に治療を行って悪い時期はないとされていますが、妊娠初期と後期の中盤以降は避けた方が無難でしょう。
ただし、急性炎症などで重篤な症状を呈している場合は母体の方に危険が生じますのでこの限りではありません。
また治療に際しては妊娠中であることを必ず歯科医師に告げて下さい。
- 妊娠中に親知らずが痛んで
きたのですが、どうすれば
いいですか? -
妊娠中に親知らずがひどく痛んだり腫れることがあります。
これは親知らずの虫歯や歯冠周囲炎が原因なことが多いです。
妊娠中の歯の治療としては、消炎処置、鎮静処置が基本ですが状況によっては外科的に抜歯をすることもあります。
親知らずをそのままおいてしまうことで問題なのが、重症感染症になる場合、顎の骨が著しく吸収して溶けてくる場合(時には骨髄炎)、副鼻腔炎(上顎洞炎)をひきおこす場合、などです。妊娠中の親知らずの抜歯は産婦人科、歯科の主治医の先生とともによく相談してから処置の時期や投薬内容の検討を行う必要があります。
- 妊娠中は歯槽膿漏が
進行しやすいのでしょうか? -
妊娠期間中は、女性ホルモンを栄養源として歯周病菌が増殖しやすい環境にあります。
丁寧なブラッシングとノンアルコールタイプの洗口剤を、併用されることもお勧め致します。また、一般的に妊娠中に限らず歯周病が進行する場合には、幾つかの原因が考えられます。
ブラッシング方法やブラッシング圧が不適切な場合、歯間ブラシの誤った使用、歯肉にダメージを与えるような歯科治療などです。歯周病治療が終了して、定期的な観察に移行している場合、月に1回のクリーニングは少し間隔が短いように思います。
実際に、月に1度のクリーニングが必要な状況であるのか再確認される必要があります。使用されている歯ブラシの硬さもチェックを受ける必要があります。
適切なブラッシング方法によって歯肉のクリーピング現象といって、歯肉が隙間を埋めるように増殖することもあります。
ブラッシング方法としては歯肉を歯の方向に押し上げるようなイメージで磨く事です。
また、歯と歯茎の境目を強くストロークすることは歯肉の退縮に繋がるので要注意です。
これらの事は、いい機会ですから歯科医院でブラッシング指導を受けてもらえらばと思います。
- 妊娠中で銀歯の粉は人体に何の
悪影響もないのでしょうか? -
妊娠期間中で色んな事に不安を感じられているようですが、口腔内で銀歯の研磨を行っても金属粉の量は100万分の1グラム単位の量だと思います。
また、その全量を体内に摂取しているとは考えられません。
銀イオンが微量で胎児に与える影響は殆ど無いと考えられます。
診療室内に一瞬、長時間いたとしても、同様な考えが成り立ちます。金属イオンの影響を心配されるのであれば、むしろ魚肉中に含まれる水銀量を心配されるほうが、一時的な歯科治療に対して心配されるよりも合理的です。
ある種の魚類(メカジキ、ミナミマグロなど)は1.0mgHg/kgと高濃度の水銀を含んでいる事が知られています。これらの食品であっても、妊娠期間中は1週間に4食(1食150gとして)は摂取しても安全であるとの勧告があります。金属であるかぎりにおいて、完全に無害なものは世の中に存在しません。
金属アレルギーが出ないと一般的に考えられている、「金」や「チタン」にもアレルギー反応を示す人はいます。
歯磨き剤にも有害だと考える事の出来る成分は含まれていますし、食品添加物の全ては安全とは断言できません。
要はリスクの発症因子がどれだけ高いとかんがえらるかが重要で、すべての事を疑いだすと完全に安全なものは存在しない事になってしまいます。
- 妊娠中、治療時のレントゲンや
麻酔は影響ないのでしょうか? -
歯科でのレントゲンの被爆線量は太陽光線から浴びる自然被爆量よりも少ないといわれています。
小さな歯のレントゲンではおおよそ0.03mSV(放射線の単位、シーベルト)で胸部のレントゲン一枚の1/20程度と考えられています。
また、腹部に照射するのではなく頭部なので散乱線の影響も無視できる範囲です。
鉛入りのプロテクターを装着して、撮影していれば妊娠に対する影響(撮影後、妊娠が判明した場合でも)も心配する必要がないというのが一般的な見解です。妊娠あるいは妊婦に対する全ての薬剤は、治療に使用する有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する事というのが最近の傾向です。
つまりは妊娠に対して100%安全な薬剤は存在しないと解釈できます。
では、必ず問題があるのかというと常に何らかのリスクがありますよというのが基本です。
実際に妊娠初期、妊娠中の歯科治療が問題になるのかというと昔に比べて、問題ないとする傾向が強く、歯周病や虫歯の痛みを放置するほうが低体重児出産や早期出産のリスクが高くなるとされています。過去の治療の影響は殆ど無視できる範囲で、心配する必要はないと考えます。
妊娠されている可能性がある場合には、より一層お口の手入れを念入りにされることをお勧めいたします。
- 妊娠したら唾液が急に
へりました。唾液がほとんど
出ません。 -
妊娠時にはホルモンバランスの変動などによって、唾液の分泌が減少することがあります。
舌の運動や唾液腺のマッサージによって反射唾液の分泌促進を行なうことが有効だと云われています。
歯ブラシや電動歯ブラシで歯肉部分をマッサージすることで、小唾液腺の分泌が刺激されるとも云われています。
特に、音波歯ブラシなどは独特の振動によって唾液の分泌促進効果が高いとされています。妊娠期間中の口腔内の清掃状態は重要なので、常に口腔内を刺激することで唾液の分泌減少に対応されることをお勧めいたします。
- つわりがひどくて歯が
みがけません。何か良い方法は
ないですか? -
できるだけ間食(特に甘いもの)を避けて、口の中に食べ物のカスがたまるのを防ぎましょう。
歯ブラシが無理であればブクブクうがいでも構いません。
気分の良いときを見計らって、できるだけ歯ブラシを使うよう心がけましょう。
もちろん歯磨き粉などは使用しなくて結構です。また、10分ほどは時間をかけて歯ブラシをしていただきたいですが、歯磨きだけをすることは大変だと思います。
ただ、歯を磨くのは洗面所だけとはかぎりません。
テレビを見ながらとか新聞、本を読みながらというのも一法です。
歯科医院で染め出しをしてもらい指導を受けると、歯磨きが難しく、その結果として時間がかかることがわかります。
歯磨き剤が多すぎると口の中が泡でいっぱいになって早くやめたくなるので気をつけましょう。

子どもの歯の治療について
- 6歳の子供の下の前歯が抜けないのに内側から永久歯が
生えてきました。大丈夫でしょうか? -
下顎の前歯の永久歯は乳歯の内側から生えてくることが多いです。そのため乳歯と永久歯がしばらく重なっていても問題ありません。
ただし、乳歯の方がグラグラしていて痛くてご飯が食べられないとか、歯磨きができないなどの困ったことがあったり、余りにも内側から生えてきていて将来の歯並びに悪い影響を与えるときは乳歯の抜歯をするときもあります。また、最近乳歯が抜けてからも永久歯が生えてこない子供さんも多くなってきました。
これは永久歯に歯肉をつきやぶって生えてくる力がないためですが、加藤総合歯科・矯正歯科ではレーザーで小さい出口を作ってあげると永久歯がちゃんと生えてきますので、お気軽にご相談ください。
- 虫歯菌は母親から赤ちゃんにうつるってきいたけれど本当ですか?
-
本当です。おなかにいるときの赤ちゃんのお口には虫歯菌はいません。
虫歯は虫歯菌が感染しておこりますから虫歯菌はいったいどこからやってくるのでしょうか?
多くは育児をするお母さんのお口の中に虫歯菌がたくさんいるとお子さんに高い確率でうつります。
口うつしで食べさせたり、大人が使った箸で赤ちゃんに食事を食べさせていると、うつることがありますから注意してください。
そのためお母さんの虫歯予防が赤ちゃんの虫歯予防につながります。子供の虫歯だけでなくお母さんの虫歯にも十分注意してください。
- 3歳の子供です。
指しゃぶりがやめられません。
歯ならびに影響があるのでしょうか -
乳児期の指しゃぶりは生理的なものですから心配はいりませんが、指にタコができるまで吸うなど程度が激しい場合や4歳をすぎてもやめられないで長期間になる場合は、あごの発達や歯並びが悪くなるなどの悪影響を及ぼすことがあります。
5、6歳以上でまだ指しゃぶりをする場合はやめさせてあげて下さい。
- 6歳の子供の生えたばかりの前歯が転んで抜けおちてしまいました。
どうしたらいいですか? -
抜けた歯をもう一度抜けた所に植え込むことができます。そのためには一分でも早く歯科医院で処置を受けることが必要です。抜けた歯は清潔にして牛乳の中、また、お母さんのお口の中(唾液の中)に入れて歯科医院に持っていきましょう。
抜けた歯を植え込んだ後は歯が再び抜けないように固定の処置をして、しばらく経過を見ていきます。そのまま経過が良ければそのまま今までどおり使ってもらえます。
ただ、一度抜けた歯や、強く打ってしまった歯は時々、半年、1年後に歯の中で化膿したり、歯の根っこが吸収してグラグラしてトラブルになることがあります。そのために定期的にしばらく経過をみていいくことが大事になります。
- 子供の口臭が気になります。胃腸など、どこか悪いのでしょうか?
-
口臭は強弱はありますが誰にでもあるものです。
特に朝起きたとき、かぜなどで体調が悪いときは強く感じることがあります。
子供の口臭は気にしないでいいことが多いですが、唾液が少なくてお口の中が乾燥すると口臭が強くなりますので、注意してみてください。
また、口臭の約8割はお口の中に原因があるといわれています。
虫歯とか、膿が出ている歯がないか、歯ぐきははれていないか、一度お子さんのお口の中をじっくりとのぞいてみてください。もし膿がでているようであれば、すぐに消毒と歯の治療をしないと永久歯に影響がでてくることもありますので注意して見てあげて下さい。
歯の根の治療で中の膿を抜けば、歯を保存することが可能です。
歯を抜かずにそのまま使っていただきます。
- 子供の歯磨きについてポイントを教えて下さい。
-
むし歯になりやすい場所は、大人も子供も同じで、奥歯の咬み合わせの溝、歯と歯の間、歯と歯肉の境目です。
お子さんの歯ブラシは、子供用のヘッドの小さい物を選んで下さい。
歯ブラシの毛先を歯の表面にきちんと当て、軽い力で小さな往復運動で磨いてください。歯肉炎にかかっていたり、歯の生え始まる時期は柔らかめの歯ブラシを使うと良いでしょう。食べたら磨くという習慣が大切です。歯磨きを習慣にするため、食事が終わったら親子で一緒に歯磨きをするなどの工夫をしてあげて下さい。また、子供はなかなかうまく磨けません。保護者による仕上げ磨きをしてあげましょう。
特に大切な第一大臼歯(6才臼歯)は、生えるのに1年~1年半くらいかかり、歯ブラシが当たりにくい時期が続きます。歯ブラシを横から入れ、咬み合わせの溝のところを注意して磨いてあげてください。また、歯の生えかわる時期は乳歯と永久歯が混在し、歯列や歯の高さが凸凹で汚れが溜まりやすく、歯ブラシが届きにくいため、仕上げ磨きが重要となってきます。
乳幼児の時から、毎日の正しい歯磨きの習慣を身につけましょう。
- 言葉が不明瞭で、
舌のすじを切ったほうがいいと言われたのですが…(3歳) -
舌小帯短縮症と言って、舌の先端部を用いて発音するラ行、タ行、サ行がうまく発音しにくいということがあります。
この発音の完成は5~6歳と言われており、その年齢まで様子を見て、音がうまく出ない時にすじを切る簡単な手術を行います。以前はメスで切除し、縫合まで必要であったため時間もかかり大変でしたが、現在はレーザーにで手術を行っていますのでほとんど痛みも出血もなく、処置時間も10分くらいで終わるため、大変喜んでいただけるようになりました。
また同じように上唇から前歯にかけてのすじが、短い場合があります。
これを上唇小帯強直症といい永久歯の前歯の歯の並びが悪くなりますので、これも同じようにレーザーにて10分程で処置が終わります。詳しくはこちらをご覧下さい。 レーザー治療による症例>>
早めにご相談下さい。
- 健診でレントゲンをとったら、
前歯に余分な歯があると言われました。(3歳) -
この余分な歯は過剰歯と呼ばれるものです。
過剰歯には、そのまま生えてくるものと生えてこないものがありますが、歯並びによくない影響を及ぼす場合、取ってあげるのがよいでしょう。
生えてこないものについては、将来にわたって歯並びに影響がないか注意深く観察する必要があります。特に多いのが上顎のちょうど真ん中の前歯の間に過剰歯が多く、これを正中埋伏過剰歯といい、前歯の歯並びに影響しやすいため、小学生のうちに摘出をしてあげたほうが良い場合があります。
また、歯並びに影響が無くても将来的に過剰歯が細菌感染をおこし、痛みや腫れなどの症状がでてくるようなら、やはりこれも摘出の処置を行わないといけなくなります。その場合放置しておくと、回りの骨や隣の永久歯に悪影響を及ぼしてしまいます。
定期的に歯科医院で調べてもらうことをお勧めします。
- 下の前歯の乳歯が抜けないのに、
内側から永久歯が生えてきました。(5歳) -
下の前歯の永久歯が乳歯の内側から生えてくることはよくあることです。
この場合、これ以上乳歯の歯根の吸収は難しいので、乳歯を抜いてもらってください。その後、永久歯は生えてくるにつれて、舌で押されて前のほうに移動してきます。正しい位置にいくかどうかは、永久歯の幅と乳歯を抜いた後の隙間の幅の問題ですので、歯医者さんに相談してください。場合によっては将来的に矯正治療が必要になってくることもあります。
また、乳歯が抜けているのになかなか永久歯が生えてこないことがあります。
これは永久歯が歯肉をつきやぶって出てくる力がないので、歯肉に出口を作ってあげないといけません。レーザーなら処置も簡単で痛みもほとんどでませんので、乳歯が抜けて一ヶ月以上永久歯の顔が見えないときは早めにご相談下さい。
- 永久歯が生えてきましたけど、
まだ指しゃぶりをしています。
止めさせた方がいいですか?(6歳) -
一般的には、乳児期の指しゃぶりは癖としてとらえるよりは、
生理的なものと考えてもよいのですが、小学校に入っても残っていると問題となるでしょう。指しゃぶりに対する見解は、小児科医や心理学者、歯科医師の立場で少し違いますが、生理的な指しゃぶりの時期(3~4歳)を越えても続く場合は、開咬(前歯が噛み合わない)上顎前突(出っ歯)の原因になりますのでやめさせたほうがよいでしょう。もし開咬や上顎前突になってしまった場合は矯正治療の適応になります。
しかし、やめさせ方によっては他の問題が起きることもありますので、かかりつけの歯科医師に相談するとよいと思います。
初期の状態であればマウスピースなどで改善する場合もあります。
- 上の前歯(永久歯)がハの字
に生えてきました。(7歳) -
上の2本の前歯がハの字(扇形)に開いた状態で生えてくることは一般的に見られる現象でこのような歯並びの時期を“みにくいあひるの子時代”とも呼んでいます。
多くの場合は、隣の歯や犬歯が生えてくることや唇と舌とのバランスで、自然に治っていきます。
しかし、
・歯の大きさと顎の大きさのバランスがとれていない(歯の大きさに比べ顎が小さいまたは大きい)
・余分な歯が埋まっている
・隣の歯が生まれつき欠如しているなどの原因がある場合、自然には治らないことがあります。
最終的には矯正治療の対象となるときもありますので一度歯科医師に相談してみて下さい。
- はえかけの乳歯は、本当にむし歯になりやすのですか?
-
はえたばかりの歯は、歯の表面がやわらかく酸に侵されやすいのです。
歯がはえてから表面が固くなってくる一年くらいの間にできる虫歯が多く、この時期にフッ素を塗るなどの虫歯予防が大切になってきます。また生活習慣で歯ブラシをしっかりさせることを覚えてもらう必要があります。
1日3食の食事の後はもちろんのこと、おやつの後のブラッシングも習慣ずけてください。それでも、虫歯になるときはありますので、定期健診のよる早期発見、早期治療が効果的です。
- 乳歯に冠をかぶせると永久歯がはえるのに邪魔になりませんか?
-
乳歯に冠をかぶせることで、とくに永久歯がはえるのに邪魔になるということはありません。
しかし、大きなむし歯などによって歯の根の先に病変があったり、根の神経をとってしまったりすることにより、乳歯の根の吸収がうまくいかなくなり、永久歯がきれいにはえてこないということもあるので、冠をかぶせなければならないような大きなむし歯をつくらないということが一番大切なことなのです。ただ、加藤総合歯科・矯正歯科では乳歯に冠をかぶせることはせずに、100%白い詰め物(レジン)にて治療しています。
- 乳歯が生えてくるのは、いつ?
乳歯が生えそろうのは、いつ? -
早いお子さんでは、4~6カ月頃、平均的には8~9カ月頃に、下の前歯(乳中切歯)から生え始めます。
上の前歯が最初に生えることもあります。この頃には、離乳食も始まり、よだれも増えてきます。乳歯は、上顎と下顎に10本ずつの計20本あります。
1歳のお誕生日の頃には上下の前歯が4本ずつ並び、その後、乳犬歯の奥の第一乳臼歯が先に生え、1歳半健診の頃に、乳犬歯が生えてきます。
2歳から2歳半頃に1番奥の第二乳臼歯が生え始め、2歳半から3歳頃に20本生えそろい、乳歯列と呼ぶ歯並びが完成します。
乳歯列では、歯と歯の間にすき間がよく見られ、大きい永久歯が生えるときに有利になっていますので、あまり気にしないようにして下さい。
幼稚園時代は乳歯列が続きますが、乳歯の下の顎の骨の中では永久歯が育っています。レントゲン写真でわかります。
- 2歳で前歯がとけてきたみたいです。
-
前歯がとけてきたようにみえるのは、むし歯であるとおもわれます。
哺乳ビンにジュース(果汁100%でも糖分にかわりはない)やスポーツ(イオン)飲料、乳酸飲料を入れて与えたり、哺乳ビンのだらだら使用によってできることが多いようです。
むし歯は、まず歯の表面が白くなり、しだいに歯が溶けたような状態になってきます。お母さんがむし歯の状態に早く気づき、早めに治療と指導を受けて下さい。
- 乳歯の歯ならびでは隙間があるといいのですか?
-
乳歯の歯ならびでは隙間(歯間空隙)があるのが正常です。
乳歯は赤ちゃん時代から使えるように、小さいあごに合った小さいものがはえてきます。成長とともにあごは大きくなりますが、歯は大きくなりませんので隙間ができるわけです。そのあと成長したあごにちょうどよい大きさの永久歯にはえ代わって隙間はなくなります。隙間がまったく見られないと将来の永久歯の歯ならびが悪く(不正咬合)なりやすいようですが、隙間があってもかならずしもきれいな歯ならびになるとはかぎりません。この時期は顎の成長を促すために、かむ回数を増やす食生活を工夫してください。
- 検診で小帯異常と言われました。大丈夫ですか?
-
形態的な異常が多いのですが、上唇小帯(上くちびるの内側のすじ)の場合は上の前歯の裏側までつながっているものを言います。
歯みがきのときに歯ブラシがあたってしまい歯みがきをいやがり、上の前歯を早いうちにむし歯にしてしまうこともあります。また、前歯の間に隙間を残すことがあります。他には、舌小帯に強い異常があると発音や飲み込みに問題をもつことがあります。歯科医院にご相談ください。加藤総合歯科・矯正歯科ではレーザーによる小帯の処置をおこなっています。
ほとんど痛みも無く、5~10分くらいで終わります。
- はえたばかりの歯は、
特にむし歯になりやすい
というのは本当ですか? -
はえたばかりの歯は、歯の表面がやわらかく酸に侵されやすいのです。
歯がはえてから表面が固くなってくる(十分な石灰化)一年くらいの間にできるむし歯が多く、この時期にフッ素を塗るなどのむし歯予防が大切になってきます。
乳歯や永久歯がすべて生え変わるのはだいたい12~13才ですから食事やおやつの後の歯ブラシは大切に行って、この間に正しい歯ブラシのやり方も覚えてもらって下さい。歯ブラシの正しい方法は歯科衛生士にご相談下さい。
- フッ素が歯にいいと聞きましたが本当ですか?
-
はえたばかりの歯は、歯の表面がやわらかく酸に侵されやすいのです。
歯がはえてから表面が固くなってくる(十分な石灰化)一年くらいの間に
できるむし歯が多く、この時期にフッ素を塗るなどのむし歯予防が大切になってきます。
フッ化物は歯の質を強くすることと、再石灰化を促進させる等で、むし歯予防において確立された方法です。
無色透明で、定期的に歯科医院で塗布する物です。主に乳歯の前歯がむし歯になった後で、進行を抑えるために塗る(銀が沈着してむし歯の部分が少し黒ずむ)、フッ化ジアンミン銀とは別の物です。
またさらにイオン導入法を併用するとより歯の中にフッ素が取り込まれ効果が高かまります。
- 子供が3歳になりますが
虫歯が急に増えてきました。 -
3歳頃になると、外に出て甘いものを口にすることが多くなってきます。
また、歯と歯の間にむし歯ができてくる時期でもあります。
乳歯のむし歯は、歯と歯の間のかくれたところで進行し、お母さんが気づいた時には大きなむし歯になっていることが多いのです。
また、乳歯の神経はまだ未熟で、あまり痛みを感じません。このことが発見を遅らせる原因の一つです。
おやつも時間を決めて与え、歯ブラシの習慣も一緒につけていって下さい。早期発見、早期治療をおこなうために、定期的な検診が必要になります。
- 乳歯の虫歯の特徴って
あるのですか? -
乳歯は永久歯に比べて軟らかく、歯の厚みも薄く小さい形をしています。
特に歯の表面の硬いエナメル質は永久歯の半分の厚さで石灰化が弱く、一度むし歯になるとその進行は早く5~6カ月で神経の近くまで進みます。神経までむし歯が広がっても、子どもはほとんど痛みを訴えないのが特徴です。そのため骨の中まで細菌が入り腫れて、初めてお母さんが気付いたりします。神経のない乳歯の根は非常に弱く、大人の歯と生えかわるまでもたないことがあります。
乳歯は小さく歯の厚みも薄いため維持が弱く、治療したものがかけたりはずれたりします。
もし、そんな場合はすぐ再治療してもらいましょう。そのままにしているとたちまち悪くなります。定期健診、早期治療が大切です。
- 1歳半なんですが
まだ哺乳瓶が手放せません。 -
なるべく早くやめるようにしたほうがよいでしょう。
哺乳ビンのダラダラ使用は乳幼児のむし歯の原因になりますし、お口のまわりの筋肉の発達にも影響がでてきます。
徐々にコップに切り換えましょう。母乳も牛乳も乳糖という糖分を含んでいますので、ショ糖ほどではなくてもむし歯の栄養源になります。
天然果汁やイオン飲料も、しっかり糖分を含んだ酸性の飲料ですので入れないでください。
麦茶でものどが渇けば飲んでくれるでしょう。
どうしても寝る前の授乳がやめられなければ、飲んだ後は哺乳ビンをはずして口の中をきれいにふいてやります。決してお口の中が汚れたまま寝かさないで下さい。
- 乳歯の虫歯は
永久歯に影響しますか? -
乳歯のむし歯は、食べ物をよく噛むことができなくなることはもちろん、正しい発音を身につけなければならない大切な時期にあり、発音の修得に悪影響を及ぼします。それに加え、乳歯のむし歯は永久歯の歯並びや咬み合わせの成立に悪影響を及ぼします。健全な乳犬歯、第一乳臼歯、第二乳臼歯の前後的な最大の幅を加えますと、これら乳歯と交換して生えてくる犬歯、第一小臼歯、第二小臼歯の前後的な最大の幅の合計よりも大きいのです。上あごで約1mm、下あごで約3mm大きく、そのために永久歯がゆっくりと、余裕をもって生えてくることができる仕組みになっています。
ところが、乳歯がむし歯になると、とくに歯と歯がお互いに接している部分では、
歯が隣の歯のむし歯の部分に入り込んでしまいます。これでは、第二乳臼歯の後に生えてくる第1大臼歯が乳臼歯を前の方向に押すため、永久歯が生えてくるスペースが不足してくるのです。そのために、永久歯が完全に生えてこなくなったり、横のほうに生えてきて、永久歯の歯並びを乱すのです。
東京歯科大学小児科講座の研究によりますと、この部位の乳歯のむし歯を予防し、健全な乳歯の状態で永久歯と交換すると、この部分の永久歯の歯並びは、ほとんど乱れないことがわかっています。
お母さん方も、この部位のむし歯を予防することの大切さを自覚してください。さらに、乳歯のむし歯が進んで、永久歯が生えてくる時よりもかなり早い時期になくなってしまいますと、永久歯があごの中に埋まったままで生えてこないこともあります。
最初から歯がなかったのではありません。第二乳臼歯が早い時期にむし歯になり、
なくなってしまったためです。そのために第1大臼歯は、第二乳臼歯のあったスペースまで前方に移動してきて第一乳臼歯に接してしまい、その結果、第二乳歯のあとに生えてくるはずの第二小臼歯があごの中に埋まったままになってしまったのです。この部分のエックス線写真をみると明らかです。
- 乳歯の根の先の病気は
永久歯に影響するのですか? -
乳歯のむし歯が進むと、歯の真中にある歯髄という軟らかい組織に炎症が波及し、
さらに進むと歯髄は死んでしまい、歯に根の先に膿の袋ができます。
乳歯のすぐ下には、永久歯の芽があります。
そのために、永久歯の芽のできはじめほど、永久歯の形成に大きな影響を与えるのです。しかし、乳歯の根の先に病気ができても、生体自体これから防御しようとする力もかなり強く、必ずしも目で見てもはっきりわかるような障害は少ないのです。しかし、皆さんは気づかなくても、永久歯の形成状態が悪くなり、むし歯にかかりやすくなることが多いので注意しなければなりません。また、膿の袋は歯槽骨という、歯を支えている骨を溶かしていきます。
そうなると、たとえ後から永久歯が生えようとしても骨と一緒に永久歯まで溶けてしまうことになります。特に前歯に多いのですが、昔に歯を打ったことがある歯も気ずかないうちに中で
化膿してくることがあります。早期の治療が必要になります。
- 一番奥の乳臼歯をむし歯で
早く抜いてしまったが、
このままでもよいですか? -
6歳臼歯の生えてくるスペースを確保し、咬み合わせをしっかり作るためには
装置を入れたほうがいいでしょう。ただし、この装置を入れたからといって、全体がよくなるというものではありません。
以前はよく用いられていましたが、最近ではケースバイケースで、微妙な診断がひつようです。歯科医によく相談し、入れる場合は定期的に管理を受けるようにしてください。
大切なのは、なるべく入れっ放しにすることです。
6歳臼歯の生えてくるスペースを確保できれば、その後の永久歯の生え変わり、
交換時期などもスムースに行われるのです。ただ、永久歯の歯並びに影響が出てくる時もありますので、その時は最終的には矯正治療が必要になるときもあります。
早期の診断が大切です。お気軽にご相談してください。
- 乳歯に冠をかぶせた時の影響は?
-
とくに永久歯がはえるのに邪魔になるということはありません。
しかし、大きなむし歯などによって歯の根の先に病変があったり、根の神経をとってしまったりすることにより、乳歯の根の吸収がうまくいかなくなり、永久歯がきれいにはえてこないということもあるので、冠をかぶせなければならないような
大きなむし歯をつくらないということが一番大切なことなのです。
もちろんむし歯はきちんとした治療がなされることが前提で、乳歯がむし歯になるということは、口の中がむし歯になりやすい環境にあるということですから、永久歯のために食生活の整備や歯磨きをして、悪い環境を改善する必要があります。
- 3歳児で虫歯の治療はできますか?
-
この時期は自我の芽生えとともに何でも一人でしたがりますが、歯の治療はお母さんと一緒がいいようです。
最初はお母さんに抱っこされて治療にのぞみますが、慣れれば一人で治療ができる年齢でもあります。「母子分離の完成はお子さんの心の中にお母さんとの絆ができたとき」とされています。母子関係が確立されている場合は、わりと早く慣れて治療室に一人で入っていきます。しかし、何がいやかもいえず、ただ泣くだけのお子さんはなかなか治療に慣れず、
いくら説明しても話を聞いてくれません。冷静になって相手の話を聞けるようになるまで、何回か来院することになるとしても、押さえつけて治療を強行することはできるだけ避けたいと考えています。つまり、お子さんが小さいうちにむし歯を進行させることをできるだけ避けてください。むし歯が軽ければ、もう少し聞き分けができる3歳6ヶ月くらいまでは、ある種のセメントをつめたりフッ化ジアンミン銀という薬を歯に塗って進行を抑えてもたせる処置もできます。
- 乳歯の外傷の影響はでますか?
-
子供さんの乳歯の外傷は、近年環境の変化からか増加の傾向があります。
乳歯の外傷は、食べ物を噛むという機能だけではなく、審美性や顔や歯並びの発育に影響を及ぼすことがあるので、外傷を受けないように、日頃から十分注意しなければなりません。
この発現頻度は、まだ運動神経の発達がにぶい低年齢児ほど高いので、この時期のお子さんをおもちのお母さん方は、環境の整備に十分気を配らなければなりません。外傷の原因は、転倒がもっとも多くなっています。
家の中で転んで、机の角などに顔をぶつけたりすることが多いので、幼児の行動範囲については、できるだけこのようなものを置かないようにすることが大切です。
乳歯が外傷を受けたとき、同時に唇や顔なども怪我したり骨を傷つけたりすることがあります。それによって顔の発育や審美性に影響も与えることもありますが、乳歯外傷の影響としてもっとも多いのは、乳歯のすぐ下にあり、発育している永久歯に影響を及ぼすことです。乳中切歯が細かく割れて一見重症に見えるものでも、この症例は、破折しただけで他の部分には大きな影響を与えていません。
これは、歯が割れることによって力が分散されたためです。
あたかも釘を金槌で打ちこんだように、上あごの乳中切歯が骨の中に埋入しているものは、エックス線写真で見ると、歯はまったく破折していません。
このような症例が乳歯では多くあります。しかし、歯は破折していなくとも、永久歯に与える影響は大きいのです。3歳児の乳歯が外傷を受けますと、永久歯が歯冠と歯根の間で曲がってしまい、口の中に生えてこないことがしばしばあります。
しかし、このような症例でも、定期的に検診を受けていれば、最適な時期に処置することによって、口の中に永久歯を誘導することもできるのです。
このような理由で、日頃の定期健診が重要なのです。これほど大きな障害にならなくても、永久歯の形成不全を起こすことはしばしばあります。障害の程度は、一般的に外傷を受けた時期が早いほど重症になり、永久歯の歯冠ができ始めた頃の外傷、つまり乳中切歯が生えたばかりの一歳未満のお子さんの場合は、まったく歯の形を呈していない歯牙腫というものになってしまうこともありますので、とくに低年齢児については、外傷を受けないよう、十分に気をつけなければなりません。